国立大学法人北海道国立大学機構オープンイノベーションセンター(ACE)
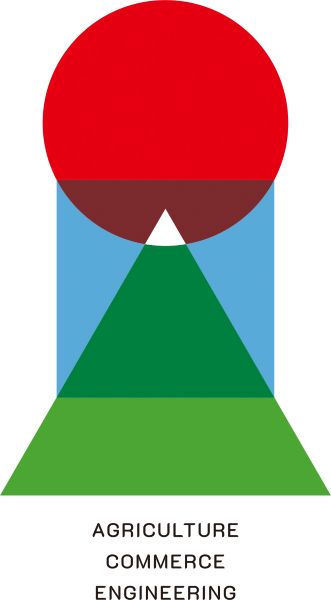
産学官金の期待に応えるオープンイノベーションの推進
本出展では三大学統合後3年半において進められてきた商学・農学・工学の分野融合型共同プロジェクトの事例の他、特長的な三大学の産学連携事業を紹介します。またこれからスタートアップを目指す案件に対し、ACEが行う各種支援について展示します。
学術・試験研究機関展示ゾーン地域活性化開発サポート・技術提案DX脱炭素/ゼロカーボン・カーボンニュートラルSDGs研究結果・研究成果
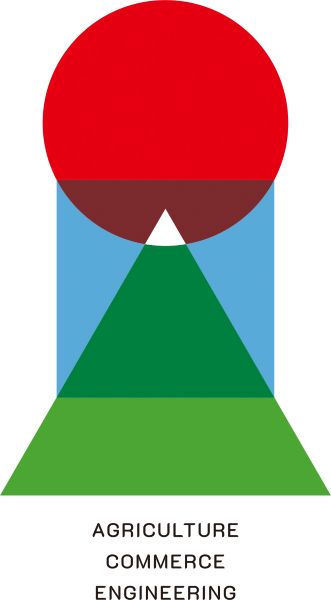
| 住所 | 〒0900013 北海道北見市柏陽町603ー2 |
|---|---|
| 電話番号 | 0157264190 |
| オフィシャルサイトURL | https://www.nuc-hokkaido.ac.jp/innovation/open-innovation.php |
| Instagramアカウント URL | |
| その他のSNSアカウント URL |
製品・サービス

社会実装の支援~ACEプロジェクトから第1号スタートアップ設立~
北海道国立大学機構は、北海道を中心に介護・福祉サービスを展開する㈱さくらコミュニティサービスとの共同研究で、人材育成・情報技術等、文理両側面から知見を提供し同社若手社員に対する新規事業開発のための研修プログラムの開発に取り組みました。
ACEは、本件に関してコーディネート業務を担当し、研究~スタートアップ設立を主導。2023年に「エイチスリー株式会社」が設立されました。
同社には、機構発第1号認定スタートアップの称号が付与されています。
https://www.nuc-hokkaido.ac.jp/news/3569/
資料ダウンロード
Zekkeiプロジェクトとは、三大学の異分野連携研究として、モバイルSINET(Science Information NETwork)とDIAS(Data Integration and Analysis System)を通信・情報基盤とした観光アプリを開発し、日本全国・世界に発展可能なデータ駆動型観光の実現を目指す取り組みです。
北海道内の自治体や観光・宿泊施設、交通機関と連携し、文理融合の研究チーム体制で課題に取り組むことで、観光資源化されていない自然現象が作り出す「偶発的な景観」を潜在的な観光資源ととらえ、「偶発的な景観」の発生を予測する自然景観予測システムを開発してこれまでにない新しい観光モデルの構築を目指します。また、「偶発的な景観」のブランド化や、VR等で体験できるようにする取り組み、さらに、観光客を能動的に誘導し、絶景の遭遇率を高め、観光地のオーバーツーリズム対策ができるようにする取り組みにより、持続的な地域活性化を目指します。
これまで、北海道東部の屈斜路湖における雲海の発生メカニズムを調査し、気温差と湿度、風速から美幌峠での雲海の遭遇期待度を予測するための取り組みを行ってきました。また、網走湾沿岸において、独自に設置した鉄塔気温計の気温差から上暖下冷の空気層の形成を捉え、蜃気楼の発生時刻、規模等の予測を行いました。これらの観測ネットワークと解析技術を活用したDIASアプリ『絶景予測‒Zekkei Explorer』(https://diasjp.net/service/zekkei/)を開発し、所定の地点における蜃気楼の遭遇期待度の予報を公開しています(運用試験中)。
3大学連携の観光プロジェクトをさらに発展させて、気象観測の空白を埋める広域・遠隔観測機器を独自に開発・運用し、信頼性の高い自然現象の遭遇予測を観光だけでなく、防災、地域交通、農業、健康等の分野に展開します。
北海道内の自治体や観光・宿泊施設、交通機関と連携し、文理融合の研究チーム体制で課題に取り組むことで、観光資源化されていない自然現象が作り出す「偶発的な景観」を潜在的な観光資源ととらえ、「偶発的な景観」の発生を予測する自然景観予測システムを開発してこれまでにない新しい観光モデルの構築を目指します。また、「偶発的な景観」のブランド化や、VR等で体験できるようにする取り組み、さらに、観光客を能動的に誘導し、絶景の遭遇率を高め、観光地のオーバーツーリズム対策ができるようにする取り組みにより、持続的な地域活性化を目指します。
これまで、北海道東部の屈斜路湖における雲海の発生メカニズムを調査し、気温差と湿度、風速から美幌峠での雲海の遭遇期待度を予測するための取り組みを行ってきました。また、網走湾沿岸において、独自に設置した鉄塔気温計の気温差から上暖下冷の空気層の形成を捉え、蜃気楼の発生時刻、規模等の予測を行いました。これらの観測ネットワークと解析技術を活用したDIASアプリ『絶景予測‒Zekkei Explorer』(https://diasjp.net/service/zekkei/)を開発し、所定の地点における蜃気楼の遭遇期待度の予報を公開しています(運用試験中)。
3大学連携の観光プロジェクトをさらに発展させて、気象観測の空白を埋める広域・遠隔観測機器を独自に開発・運用し、信頼性の高い自然現象の遭遇予測を観光だけでなく、防災、地域交通、農業、健康等の分野に展開します。
家具等に使用される北海道産広葉樹は、ウッドショック等の影響で不足しており、銘木市等において高値で取引されています。一方、道産広葉樹の多くは、山元で価値が精査されないまま、バイオマス発電のためのチップ材として出荷される等しています。
良質な北海道産広葉樹を、より付加価値の高い製品を生み出す「川下企業(家具業界等)」に届けるためには、「川上(山元)」に存在する広葉樹に関する的確な情報を把握する必要があります。広葉樹について、胸高直径、枝下通直性、樹種といった情報を得ることが重要ですが、広葉樹は針葉樹と異なり、枝葉が広がっているため、無人航空機UAV等による上空からの撮影では情報の取得が困難です。
そこで、地上からの林地調査手法として、360度カメラ付きバックパック型3Dスキャナーによる撮影を行い、胸高直径および枝下通直性のデジタル保存方法の確立と検証を行っています。これにより、胸高直径、樹皮の状態、幹の形状、森林の3Dマップ等の情報を組み合わせた、視覚的にわかりやすいデータを取得でき、樹木全面の情報をPC上で容易に閲覧可能となります。
北海道産広葉樹の情報共有システムを構築することにより、北海道産素材の高付加価値活用、サプライチェーン最適化による物流コストの削減、DX化及び適正取引による林業の担い手不足の解消、森林の適正管理といった地域課題、社会課題の解決を目指します。
良質な北海道産広葉樹を、より付加価値の高い製品を生み出す「川下企業(家具業界等)」に届けるためには、「川上(山元)」に存在する広葉樹に関する的確な情報を把握する必要があります。広葉樹について、胸高直径、枝下通直性、樹種といった情報を得ることが重要ですが、広葉樹は針葉樹と異なり、枝葉が広がっているため、無人航空機UAV等による上空からの撮影では情報の取得が困難です。
そこで、地上からの林地調査手法として、360度カメラ付きバックパック型3Dスキャナーによる撮影を行い、胸高直径および枝下通直性のデジタル保存方法の確立と検証を行っています。これにより、胸高直径、樹皮の状態、幹の形状、森林の3Dマップ等の情報を組み合わせた、視覚的にわかりやすいデータを取得でき、樹木全面の情報をPC上で容易に閲覧可能となります。
北海道産広葉樹の情報共有システムを構築することにより、北海道産素材の高付加価値活用、サプライチェーン最適化による物流コストの削減、DX化及び適正取引による林業の担い手不足の解消、森林の適正管理といった地域課題、社会課題の解決を目指します。
飼料収穫の現場では、収穫、運搬時にハーベスタと並走して原料を受け取り、運搬するトラックの運転手が不足しており、また、経験の少ない運転手では、並走するハーベスタとトラックの位置関係や飼料の積載状況の把握、積載後の運搬において道路情報に応じた適切なルートの把握が難しいという課題があります。
そこで、収穫時におけるハーベスタと伴走するトラックの距離や位置関係を表示することで一定に保つことをサポートする運搬用トラック伴走サポートシステムと、運搬用トラックナビゲーションシステムの開発を行っています。
運搬用トラック伴走サポートシステムにより、3D-LiDARとカメラを用いてハーベスタからトラックに計測情報を配信し、Webアプリ上でハーベスターから見たトラックの位置を把握できるようにするとともに、運転中に荷台の中を見えるようにすることで、積載状況を把握できます。
また、運搬用トラックナビゲーションシステムにより、GPSアプリで取得されるトラックの走行情報、既存の道路情報を用いて、農道に対応した運搬トラックの適切なルートを把握できるとともに、自車以外にもアプリを利用する車両の位置を地図上に可視化して確認できます。
このようなシステムをJAや企業と連携して開発することにより、経験の少ない運転手でも運搬作業に従事できるようになり、運転手不足が解消され、適切な積載状況で原料を運搬可能になります。
システムの導入によって現地での実証をすすめるとともに、生じる現場の要望をアンケート調査により把握し、さらにユーザビリティを高めたシステムの商品化と飼料収穫現場への導入・普及を行います。
そこで、収穫時におけるハーベスタと伴走するトラックの距離や位置関係を表示することで一定に保つことをサポートする運搬用トラック伴走サポートシステムと、運搬用トラックナビゲーションシステムの開発を行っています。
運搬用トラック伴走サポートシステムにより、3D-LiDARとカメラを用いてハーベスタからトラックに計測情報を配信し、Webアプリ上でハーベスターから見たトラックの位置を把握できるようにするとともに、運転中に荷台の中を見えるようにすることで、積載状況を把握できます。
また、運搬用トラックナビゲーションシステムにより、GPSアプリで取得されるトラックの走行情報、既存の道路情報を用いて、農道に対応した運搬トラックの適切なルートを把握できるとともに、自車以外にもアプリを利用する車両の位置を地図上に可視化して確認できます。
このようなシステムをJAや企業と連携して開発することにより、経験の少ない運転手でも運搬作業に従事できるようになり、運転手不足が解消され、適切な積載状況で原料を運搬可能になります。
システムの導入によって現地での実証をすすめるとともに、生じる現場の要望をアンケート調査により把握し、さらにユーザビリティを高めたシステムの商品化と飼料収穫現場への導入・普及を行います。